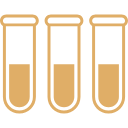 環境技術解説
環境技術解説
ESCO事業とは、省エネルギーの改修経費をエネルギー削減からまかなう、省エネサービス事業である。ESCO事業者が省エネルギーに関する包括的サービスを顧客に提供し、実現した省エネルギー効果(導入メリット)の一部を報酬として受け取る。
この記事では、ESCO事業の概要を紹介した後、最近の動向、公共事業や家庭部門における導入、今後の展望について紹介する。
※掲載内容は2023年3月時点の情報に基づいております。
※外部リンクは別ウィンドウで表示します
ESCO(Energy Service Company)事業は、1970年代の石油危機による原油価格の高騰を契機として米国で誕生し、本邦でも広がりを見せた「省エネルギーサービス事業」である。ESCO事業者が省エネルギーに関する包括的サービスを顧客に提供し、改修に必要な経費を顧客のエネルギー削減からまかなうビジネス形態を指す。
一般的な省エネルギー改修工事の場合、設計、工事、設備の運転管理のそれぞれの契約は別々となることが多いため、省エネルギー効果が保証されるわけではない。しかし、ESCO事業の場合は、省エネルギーの予備診断、詳細診断、実施計画の立案、施工、省エネルギー効果の計測・検証などを一括して請負うため、省エネルギー効果の保証が可能となる。さらに、設備の運転管理・保守・点検まで契約に含めることもでき、より多くのメリットを期待することができる(図1)。

図1 一般的な省エネルギー改修工事とESCO事業の比較
出典:(一社)ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会「ESCO事業のススメ」
ESCO事業では、省エネルギーで実現する経費節減分で省エネルギー投資をまかなうために、顧客に新たな費用負担が発生しない。また、省エネルギー効果の保障を含む契約形態をとることによって、顧客の利益の最大化を図ることができるという特徴がある。もし省エネルギー効果が発揮できず、顧客が損失を被るような場合には、これをESCO事業者が補填する。こうした契約は一般的に「パフォーマンス契約」と呼ばれ、ESCO事業の重要な要素になっている(図2)。

図2 ESCO事業の仕組み
出典:(一財)省エネルギーセンター「ESCO導入のてびき(自治体向け)」
ESCO事業は、わが国では1990年台半ば頃から注目されるようになり、1996年に資源エネルギー庁内に「ESCO検討会」が設置されて以降、行政や民間企業の間で急速に関心が高まった。1999年には、ESCO事業の普及・啓蒙、省エネルギーの推進や新技術の開発支援などを目的としたESCO推進協議会(現・ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会)も発足した。
また、ESCO事業による省エネルギー効果は、顧客のコスト低減だけではなく、発電所における化石燃料の消費削減、すなわち温室効果ガスの排出削減にも寄与している。
ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会が115社を対象に行った市場調査によると、2020年度のESCO事業の受注額は482億円で、エネルギーマネジメント事業(374億円)を超える金額になっている(図3)。ESCO事業では産業部門のエネルギー・サービス・プロバイダー(ESP)・ユーティリティサービス(シェアード・セイビング型、SSC)、産業部門のESP・ユーティリティサービス(SSC)の順に大きい。

図3 ESCO・エネルギーマネジメント事業の契約・売上金額(2020年度)
出典:(一社)ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会「ESCO・エネルギーマネジメント事業の市場動向」
ESCO事業の市場拡大を図る上で、国及び自治体などの公共機関における導入促進は、重要な課題の1つである。自治体のESCO導入件数は、2005年度は38件、2006年度は50件と公共機関でESCO事業を導入した事例は少なかった。
資源エネルギー庁では、「自治体ESCO導入のためのモデル公募要項集」を2007年4月にまとめ、自治体がESCO事業を導入する際の支援情報として提供を行った。また、環境省では、地方公共団体によるエネルギー対策を促進するために、2007年度から、「公共・公益サービス部門率先対策補助事業」を実施し、ESCO事業の普及に取組んだ。
近年においては、先進地の大阪市だけでも延べ60施設(令和2年度実績値)で導入されるなど普及が進んでいる。一方、長期の計測検証・保証義務が自治体のESCO事業のリスク要因となっているとの指摘もある。
新潟県柏崎市の公共施設「柏崎海洋センター シーユース雷音」では、ESCO事業を活用した公共施設のZEB改修を行っている(図4)。コージェネレーション・空冷ヒートポンプを中心とした熱源・給湯・昇温システムの再構築、LED照明、ペレットストーブ、BEMS装置等の導入、窓断熱強化(高性能遮熱断熱サッシ、Low-E複層ガラス)等により一次エネルギー削減率51%を達成し、ZEB Ready※を実現したという。なおこの改修におけるZEB関連設備については補助金を利用している。

図4 柏崎海洋センター シーユース雷音
出典:環境省「ZEB PORTAL」コラム『ESCO事業を活用した公共施設のZEB改修』
滋賀県では、家庭部門におけるESCO事業の普及を図るため、「家庭版ESCO事業」に取り組んでいる。この事業スキームは、環境省の平成18年度第6回NGO/NPO・企業の環境政策提言で最優秀賞を受賞したもので、提言の実現に向けて、びわこ銀行、滋賀県電器商業組合、滋賀県、滋賀県地球温暖化防止活動推進センターによる滋賀県家庭版ESCO推進協議会が、2007年7月に設置された。協議会では現在、環境省の支援を受けてパイロット事業を展開している。
この事業は、行政機関、金融機関、地域の家電販売店などが連携し、地域密着型の省エネ診断や、優遇金利による省エネ製品買換ローンを提供することで、家庭部門においてエネルギー消費の大きい給湯器やエアコンなどを省エネ製品に転換する(図5)。

図5 家庭版ESCOのイメージ(フロー図)
出典:滋賀県家庭版ESCO推進事業
省エネ製品が比較的高額であるがゆえに、導入が難しいとされていた家庭部門へのESCO事業に取り組む本事業は、地域商店の活性化の視点からも関心が寄せられている。
<事業の流れ>
省エネルギーに果たすESCO事業の役割や重要性に対する認識は定着しつつある。過去には、環境配慮契約法(2007年11月施行)に基づく基本方針のなかでもESCO事業の必要性や意義、導入フローが示された。近年では、ESCO事業を活用したZEB改修など、新しい視点でESCO事業が活用されている。
またIoTによる運用改善を併せて行うことでESCO事業の採算性を改善していくことができるとの指摘もある。例えば、建築各所にセンサーを配してデータ解析を行い、空調や照明の調整を行うことが一般的になってきている。加えて、最適制御をするための機械学習プロセスが動いていくことも想定される(併せて「ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)」も参考にされたい)。
これからのESCO事業には、従来のような熱源設備の更新を主体とした内容に加え、企画力や資金調達力などを備えた総合的なエネルギー・コンサルティングとしての役割が求められている。
・環境省「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料(案)」(PDF)
・環境省「ZEB PORTAL」コラム『ESCO事業を活用した公共施設のZEB改修』
・(一社)ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会 公表資料等
・田邊・近本「ESCO事業の長期性能検証(第1報)ESCO事業の省エネ改修手法のコストパフォーマンスと安定性」空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集(2014.9.3-5(秋田))
・野城「建築分野におけるカーボン・トレーディング導入の道筋・意義」生産研究73巻4号(2021)